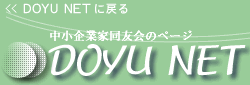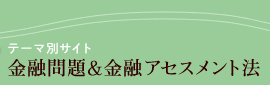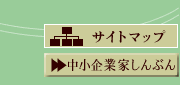Q4 金融アセスメント法の具体的な仕組みはどのようなものですか。
金融機関の公共性を発揮させ、金融システムを中小企業と地域にとって健全かつ社会的に望ましいものにするために、以下の7点を法的に規定します。
- 金融アセスメント委員会を設置すること(同友会案では、都道府県ごとに地域・中小企業金融活性化評価委員会を設置し、その総合的な連絡調整のために全国委員会を内閣府の外局として設置)。
- アセスメント委員会は、「地域への円滑な資金供給」や「利用者利便」の観点から必要な情報を収集し、金融機関の活動について評価すること。
- アセスメント委員会が収集した情報(ただし公開するにふさわしくない一部の情報を除く)および評価の結果を、評価対象金融機関に伝えるとともに、下記(4)の審査会の審査を経た後、金融システムの利用者たる国民に適切な方法で開示すること(インターネット等)。
- 金融機関の活動に関するアセスメント委員会の評価について、その正当性を審査する審査会を設置すること。
- 評価対象金融機関はアセスメント委員会の評価に不服がある場合には、審査会に再審査を要求することができる。
- 評価対象金融機関が合併等の申請を行った際には、監督官庁はその認可の可否にあたって、アセスメント委員会の評価を考慮に入れるものとすること。
- アセスメント委員会は、評価の検討の際に必要に応じて地域住民が参加する公聴会を開き、利害関係人の意見を聞くことができる。審査会は、評価結果を開示後、当該金融機関の利用者から異議申し立てを受け、評価を見直することができること。
このように、金融アセスメント法制度の手法は、行政的規制の強化でなく、金融機関の自主的な取り組みを事後的に評価し、選択を利用者の判断にゆだねるソフトなシステムの法律です。