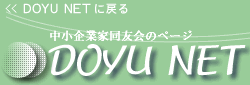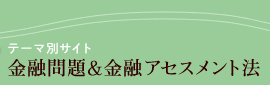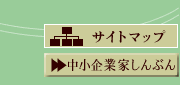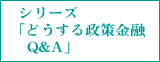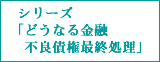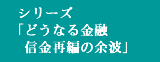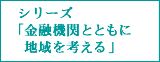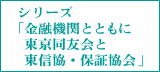シリーズ4
逃げる優良顧客
「地域密着」が形骸化の懸念
都内信金合併 (中)
「多くの中小企業や銀行がつぶれる」「貸し渋りがひどくなる」「さらに不況になる」「得意先の倒産が起こらないか不安」。これは石川同友会が10月に行った会内景況調査の特別項目「不良債権処理がさらに積極的に進められることについて」に寄せられた意見の一部です。不良債権処理とともに金融機関再編が進められており、急激な地域金融機関の変化が、地域経済への不安をあおっています。都内信金合併はペイオフ解禁を背景に急激に進められる傾向にあり、水面下の動きも気になるところです。
来年7月には王子を存続金庫として、太陽、荒川、日興の4信金が合併され、預金量2兆3000億円規模となります。
合併促進する信金中金
そのうちの1つ、預金量5000億円の荒川信金は、荒川区を中心に30支店、3出張所を持っています。
今年度3月末の決算前に信用金庫のセントラルバンクである「信金中央金庫」から「経営力強化制度」の一環で、劣後ローンの供与として26億円の資本注入を受けました。信金中金は、経営が厳しいとされる金庫から経営健全化計画を提出させて審査し、劣後ローンの供与や優先出資の引き受けで、資本増強を図っています。
荒川と同時期に王子も50億円の資本注入を受けています。これは「信金中金からの資本注入を受けた信金で、合併していない信金はない」という話を、裏付けるものであり、信金中金理事長の宮本保孝氏がもとは旧大蔵省銀行局長であったことからしても、金融庁が促進している金融機関の合併促進策に一役買っているとも言えます。
「経営健全化」で、大手行と同様に次々と信金の合併再編が促進されていく中、地域密着型である信用金庫の本来の役割が見えなくなって来ていることは、現場の融資担当者の話からも伺えます。
「合併へ向け、支店の3割減と職員の約1000名の削減の方向で進められ、地域を回れる信金マンの数も減り、企業を細やかに見て、経営者の人となりを知る担当者はさらに少なくなる。また、融資の基準を、査定が厳しいといわれる存続金庫に合わせることになれば、企業育成どころか、現状の融資が続けられるかどうかも分からない。すでに営業の中心は『保証協会付』融資と『住宅ローン』になっています」
信金とともに育って
(株)エビスヤ(山岸健一社長、東京同友会会員、缶製品卸)の会長である山岸富二氏は、荒川信金監事を務めています。氏は「創業当時月商80万円のときに300万円融資しくれたのが荒信でした。当時の融資担当者はのちに理事長となり、私も荒信の経営者のファンクラブ『親交会』を立ち上げ、地元の力のある経営者を誘いました。融資担当者の人とは家族ぐるみの付き合いで、地域のこともよく話しました。今は無借金経営ですが、ここまでこれたのも荒信のおかげ」と当時を振り返ります。
「信金の『杉の子会』では社員の家族も含めて、みんなで万博に行ったのをよく覚えています」というのは現社長の健一氏。「以前は荒信を中心に会社や社員、その家族までがつながって、コミュニティを作っていたようです。会長の意向もあって、当社の預金の8割は今でも荒信。でも最近は、集金に来る担当者も画一的な対応になり、会社の状況を聞かれることもありません。今は地銀の営業が活発で…」。
信金再編の不安定な状況に、他の金融機関が優良な顧客に積極的な営業をかけています。信金が丁寧に育ててきた優良な顧客が奪われ、経営基盤を足もとからすくわれる状況が、金融機関の多い都内で鮮明になってきているようです。
中同協事務局 平田美穂